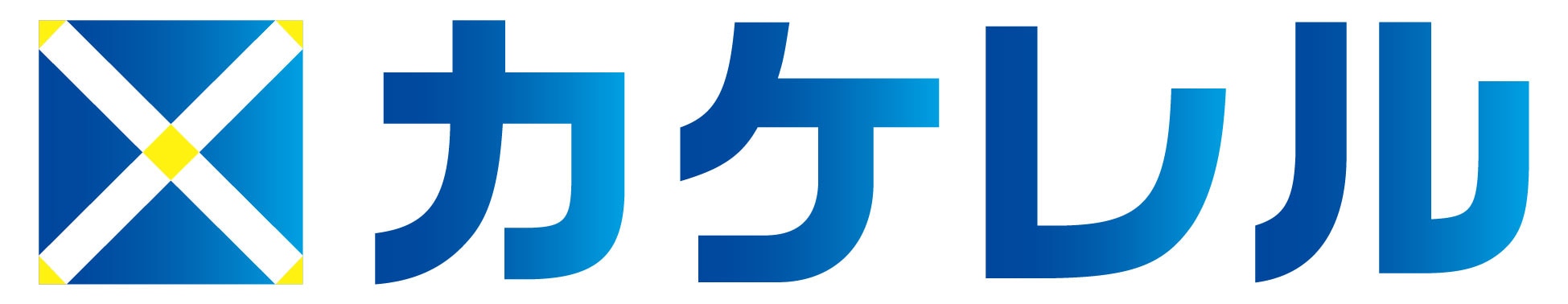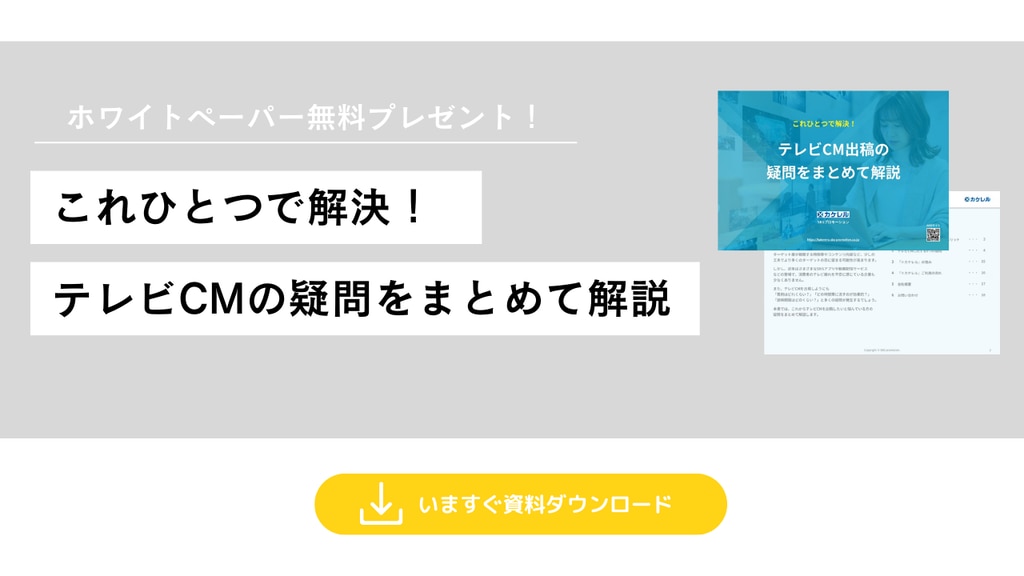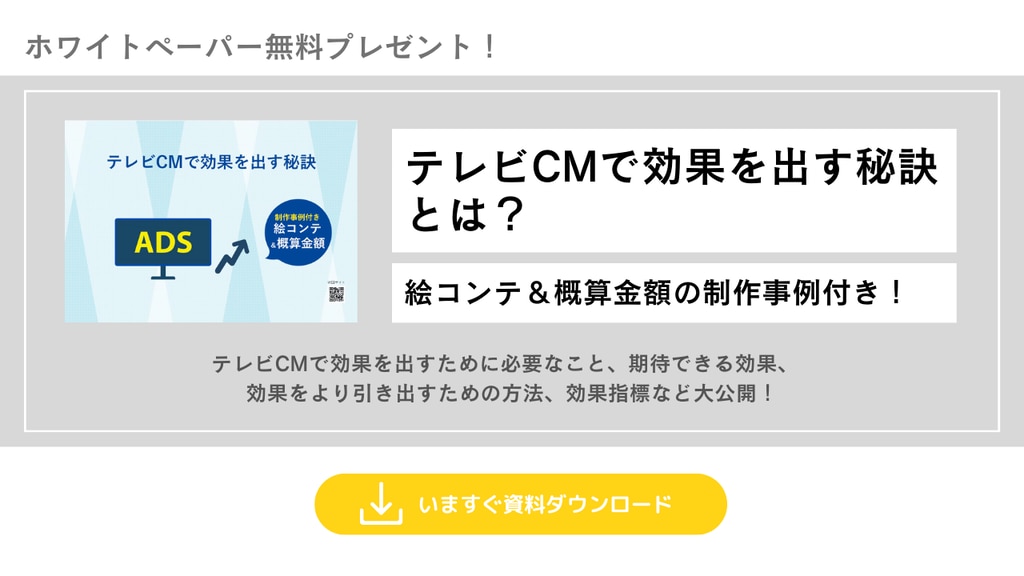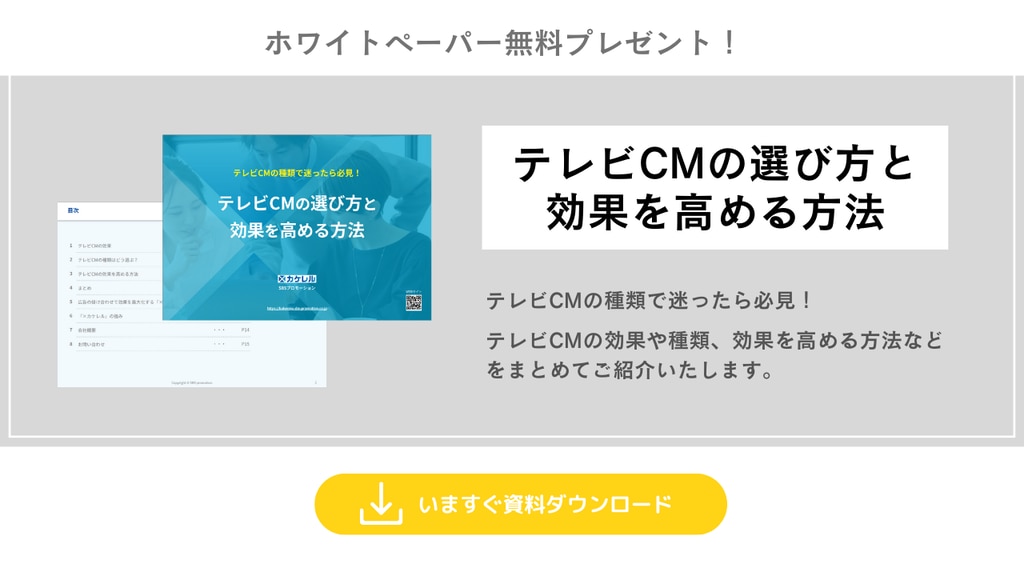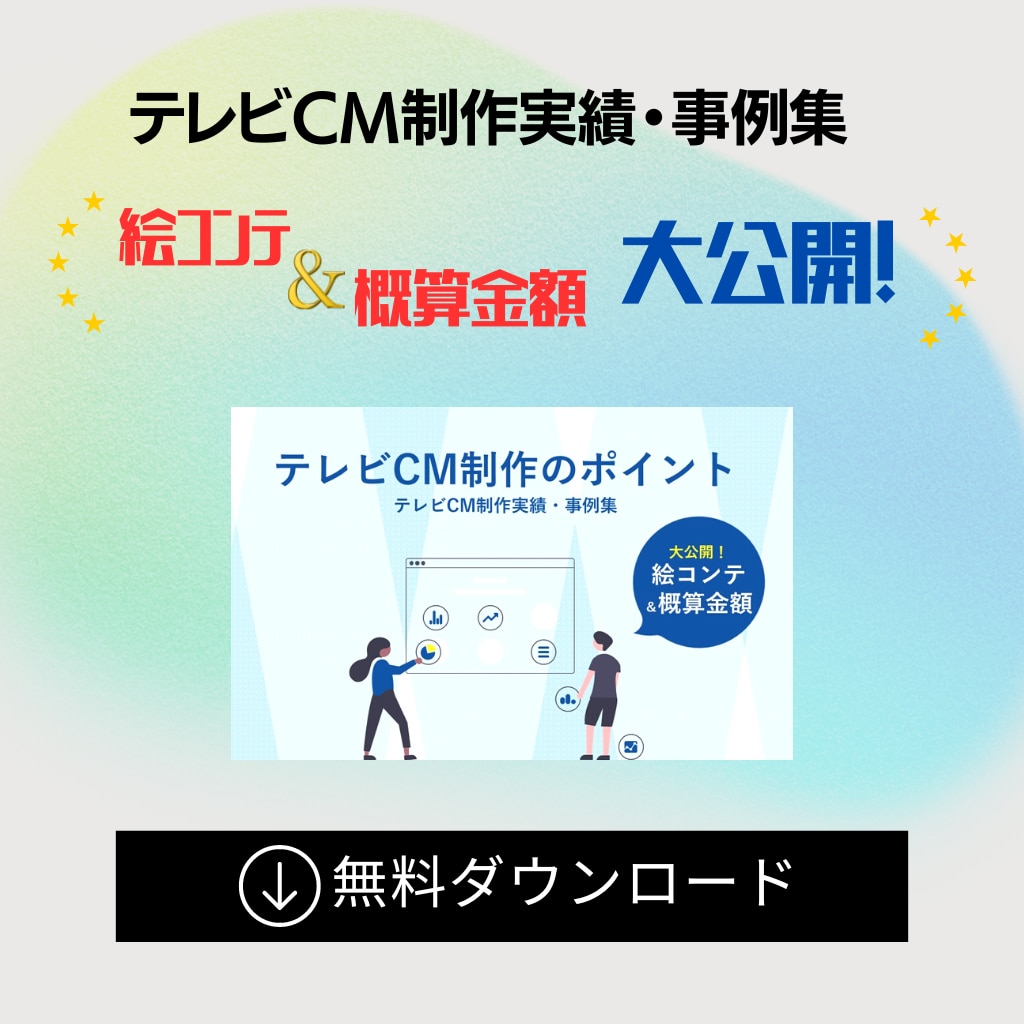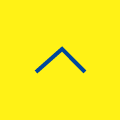テレビCMの効果測定をPRPを用いて実施する方法。そのほかの指標とは
※2024年6月5日更新
デジタル化によってインターネットの活用が進む一方、テレビは情報収集や娯楽として幅広い世代に利用される主要なメディアとして確立しています。
番組の放送中にテレビCMを流すことで、多くの視聴者に対して効率的にアプローチを行えるため、認知の拡大やブランドイメージの向上などにつながると期待できます。
しかし、テレビCMにおいては、インターネット経由で配信するデジタル広告と比べて「反響がどれくらいあったのか」を把握することは難しいとされています。
企業のマーケティング部門や広報部門の担当者のなかには、「テレビCMの効果測定はどのように実施するのか」「効果測定を行う指標には何があるのか」と気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、テレビCMの効果測定に用いられるPRPやそのほかの指標、効果測定のポイントについて解説します。
目次[非表示]
テレビCMの効果測定が難しい理由
テレビCMでは、インターネット上で配信するデジタル広告のようにユーザーの属性や行動履歴などの細かなデータを取得できないことから、効果測定が難しいといわれています。
デジタル広告には解析ツールが組み込まれており、以下のような詳細な情報を広告ごとに取得することが可能です。
▼デジタル広告で取得できる情報例
- 広告のクリック/視聴/表示回数
- 広告をクリック/視聴した人の属性(年齢や性別など)
- 広告ページでの閲覧箇所・滞在時間
- 広告経由でのコンバージョン数(問い合わせや購入など)
- コンバージョンに対するコスト など
これに対してテレビCMでは、「視聴者が実際にテレビCMを見たのか」「テレビCMで認知や購買行動につながったのか」といったデータを取得することが難しく、費用対効果が見えにくい課題があります。
効果測定を行う際には、テレビの視聴率を基にリーチ数を測定して、テレビCMの出稿前後で消費者行動を比較することが基本となります。
なお、テレビCMの費用対効果を最大化する方法については、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
PRPを用いた効果測定の方法
テレビCMの効果測定に用いられる指標として、現在主流とされているのが“PRP”です。PRPとは、Persons Gross Rating Point(パーソンズ・グロス・レーティング・ポイント)の略語で“個人の延べ視聴率”を意味します。
調査対象となる世帯のうち、特定の時間帯に個人がどれくらいテレビを視聴していたかを示す割合となり、年齢・性別ごとの視聴率を把握する際に用いられます。
PRPの区分
PRPによる効果測定では、テレビの視聴者層を年齢・性別でいくつかのグループに区分して視聴率を算出します。代表的な区分は、以下の8つとなります。
▼PRPの区分方法
区分 |
対象 |
|
C層 |
4~12歳の子ども |
|
T層 |
13~19歳の少年・少女 |
|
F層 |
F1層 |
20〜34歳の女性 |
F2層 |
35〜49歳の女性 |
|
F3層 |
50歳以上の女性 |
|
M層 |
M1層 |
20〜34歳の男性 |
M2層 |
35〜49歳の男性 |
|
M3層 |
50歳以上の男性 |
|
年齢・性別ごとに個人の視聴率を算出することで、よりターゲット層への露出を増やせる番組や時間帯にテレビCMを出稿できるようになり、費用対効果の向上を図れます。
PRPの測定方法
PRPを測定する際は、番組視聴率とCMの平均視聴率に対してCM枠の発注金額で割った値を算出します。
▼PRPの計算式
PRP=CM枠の発注金額÷P(※1)+C7(※2)
例えば、150万円のCM枠に放映し、番組視聴率とCMの平均視聴率を足した割合が5%だった場合、[150万円÷5%=30PRP]となります。
テレビを視聴した人数については、調査対象となる世帯にPM(ピープルメータ)システムを設置して集計する方法が一般的です。
家族のなかでテレビを視聴している人が専用機器で自分のボタンを押すことにより、「誰がいつ、何の番組を見ていたか」を把握できるようになります。
そのほかPRPの測定方法には、テレビの視聴に関する調査表を各世帯に配布して、個人単位でテレビを見た時間や番組などを記入してもらう方法があります。
※1・・・Program Rating(番組視聴率)のこと
※2・・・7日間以内のCM平均視聴率のこと
テレビCMの効果測定に用いるそのほかの指標
テレビCMの効果測定には、PRPのほかにGRPやGAPといった指標を用いる方法もあります。
GRP
GRPは、Gross Rating Point(パーソンズ・グロス・レーティング・ポイント)の略語で“延べ視聴率”を意味します。
個人単位で延べ視聴率を算出するPRPに対して、GRPでは「世帯でどれくらいテレビを視聴していたか」といった平均視聴率を用いて算出することが特徴です。
テレビCMを放映した一定期間における延べ視聴率を合計して算出します。
▼GRPの計算式
GRP=平均視聴率×放送回数
例えば、平均視聴率15%のテレビ番組が放映されているときに2回のテレビCMを出稿した場合のGRPは、[15%×2回=30GRP]となります。複数の番組でテレビCMを放映した場合には、それぞれの延べ視聴率を算出して合計します。
GRPの数値が高くなるほどテレビCMの露出度が高く、より多くの人に見られていると判断できます。ただし、番組を録画してテレビCMを飛ばしていたり、CM中にスマートフォンを触っていたりと、実際にテレビ画面を見ていない人もGRPにカウントされます。必ずしもGRPが正しいとはいえないため、注意が必要です。
なお、平均視聴率については、PMシステムによる集計のほか、各世帯に視聴率を測定する機器と測定データの取得・蓄積を行える“オンラインメータシステム”を設置して、自動で集計する方法もあります。
GAP
GAPは、Gross Attention Point(グロス・アテンション・ポイント)の略語で“延べ注視量”を意味します。
テレビの延べ視聴率ではなく、GAPでは「どれくらいの人がテレビ画面を注視しているか」を毎秒単位で測定するため、テレビCMに接触した視聴者の割合を把握できることが特徴です。
▼GAPの測定方法
顔認証技術を用いたセンサーカメラを各家庭のテレビに設置して、画面を注視している人を測定する
「テレビをつけていても実際に視聴者が画面を見ているか分からない」といったGRPの不確定要素を補う新たな手法として活用が期待されています。
テレビCMの効果はクロスチャネルでの検証がポイント
テレビCMの効果測定を行う際は、テレビの視聴率だけでなくインターネット上のメディアも含めたクロスチャネルでの検証を行うことがポイントです。
クロスチャネルとは、オフライン・オンラインのさまざまなメディアを横断してデータの管理や連携を行う運用体制を指します。
消費者が商材を認知してから購買行動に移すまでのプロセスでは、複数のメディアを経由することが一般的です。
▼テレビCMとほかのメディアを横断した購買行動の例
- テレビCMを見て気になった商品を公式Webサイトで調べる
- テレビCMで知ったSNSのキャンペーンに参加する
テレビCMそのものの効果だけでなく、デジタル広告やSNS、Webサイトでの行動変容を分析することで、広告による効果を包括的に把握できるようになります。
▼クロスチャネルでの効果測定に活用できる指標例
- 検索エンジンの指名検索数
- Webサイトへのアクセス数
- SNSでのキーワード検索数
- 店舗アンケートによる来店理由 など
テレビCMの放送後に検索エンジンやSNSで検索数が増えたり、Webサイトへのアクセス数が増えたりした場合には、認知の獲得につながったと考えられます。
まとめ
この記事では、テレビCMの効果測定について以下の内容を解説しました。
- テレビCMの効果測定が難しい理由
- PRPを用いた効果測定の方法
- テレビCMの効果測定に用いるそのほかの指標
- クロスチャネルでの検証方法
テレビCMの効果測定は、PMシステムまたはアンケート調査によってPRPを算出する方法が主流となっており、そのほかにもGRPやGAPといった指標があります。
効果測定の精度を高めるには、複数の指標を組み合わせるとともに、インターネット上のメディアを含めたクロスチャネルで購買行動の変化を測定して、テレビCMの反響を分析することがポイントです。
SBSプロモーションでは、複数の広告媒体を掛け合わせるソリューションサービス『×カケレル』を提供しています。テレビCMをはじめとするマスメディアやデジタル広告などの多様な媒体を活用して、広告効果の最大化につなげます。
詳しくは、こちらの資料をご確認ください。